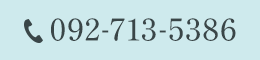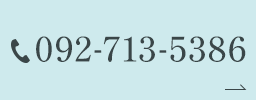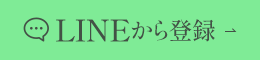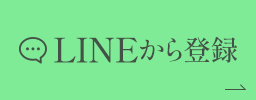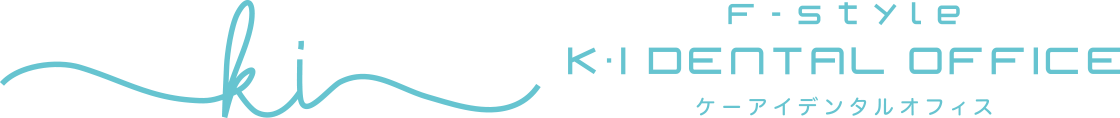妊婦歯科健診
福岡市妊婦歯科健診について

当院は、福岡市が行っている「妊婦歯科健診(無料)」の実施医療機関です。
福岡市にお住まいの妊婦さんは、当院で無料の歯科健診を受けることができます。妊娠中から産後までのお口のケアは、お母さまだけでなく赤ちゃんの健やかな成長にもつながります。安定期(4~7か月頃)に入られたら、ぜひお早めに健診をご利用ください。
| 対象者 | 福岡市内に在住の妊婦の方 |
|---|---|
| 回数 | 妊娠期間中に1回 |
| 受診方法 | 事前にご予約頂き、ご来院時に母子健康手帳をご持参ください。 |
| 料金 | 無料 |
| 健診内容 | 歯と歯ぐきのチェック、お口の相談 |
お母さんと赤ちゃんのお口の健康を守るために

妊娠中はホルモンバランスの変化やつわりなどにより、むし歯や歯周病が進行しやすい時期です。
妊娠性歯肉炎を発症しやすく、唾液の量が減少してお口の中はネバネバしているため、細菌が活動しやすい口腔内になっています。
また、つわりによってお口の中に酸が増え、歯が溶けやすく虫歯になりやすい環境になります。
お母さんのお口の健康は、おなかの赤ちゃんの健やかな成長にも関係しています。安心して出産を迎えるために、マタニティ歯科で定期的なチェックとケアを行いましょう。
実はつながっている!ママの歯と赤ちゃんの健康
妊娠中や子育て中のママのお口の健康は、赤ちゃんの成長や健康に大きく関わっています。例えば、歯周病は早産や低体重児出産のリスクを高めることが報告されています。
また、むし歯の原因となる菌は唾液を介して赤ちゃんに移るため、ママがむし歯を予防・治療しておくことが赤ちゃんのむし歯予防につながります。
さらに、口腔内の状態が良いと、しっかり食事がとれ、母体の栄養状態も整いやすくなります。
つまり、ママ自身のお口のケアは、赤ちゃんの健やかな成長のためにも欠かせない大切な習慣です。
妊娠中に多いお口のトラブル
妊娠中は、お薬に制限があったり効きにくくなることがあります。
痛みが出る前の予防と早期発見がとても大切です。
妊娠性歯肉炎
 妊娠中はホルモンバランスの変化により、歯ぐきが腫れやすく出血しやすい状態になります。
妊娠中はホルモンバランスの変化により、歯ぐきが腫れやすく出血しやすい状態になります。
初期には自覚症状が少ないこともありますが、放置すると炎症が進み、歯周病の原因にもなるため注意が必要です。
定期的なチェックと丁寧なブラッシングで予防しましょう。
※痛みが出てしまってもお薬に制限ができて効きにくいことも。
むし歯のリスク増加
 つわりや食生活の変化で歯みがきが難しくなると、歯の表面に汚れが残りやすくなり、むし歯ができやすくなります。
つわりや食生活の変化で歯みがきが難しくなると、歯の表面に汚れが残りやすくなり、むし歯ができやすくなります。
少量でも糖分を含む飲食物を頻繁に摂ると、むし歯のリスクが高まるため、ケアと食習慣の工夫が大切です。
※痛みが出てしまってもお薬に制限ができて効きにくいことも。
歯周病の進行
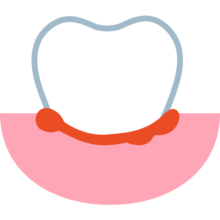 妊娠中はホルモンの影響で歯ぐきが腫れやすく、炎症が起こりやすくなるため、歯周病が進行しやすくなることがあります。
妊娠中はホルモンの影響で歯ぐきが腫れやすく、炎症が起こりやすくなるため、歯周病が進行しやすくなることがあります。
歯周病は歯ぐきの腫れや出血だけでなく、重症化すると歯を支える骨にまで影響することがあります。
また、歯周病は早産や低体重児出産のリスクを高めることも報告されているため、妊娠中の予防と定期的なチェックが重要です。
口内炎・口臭
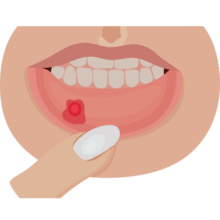 妊娠中はホルモンバランスの変化や体調の不安定さ、妊娠に伴う心理的変化(不安や緊張など)、免疫力の低下などにより、口内炎ができやすくなることがあります。
妊娠中はホルモンバランスの変化や体調の不安定さ、妊娠に伴う心理的変化(不安や緊張など)、免疫力の低下などにより、口内炎ができやすくなることがあります。
また、唾液の分泌が減少しやすくなり、唾液の量や流れが変化することで、口臭が強くなることがあります。
マタニティ歯科の治療について
妊娠中の治療に最適な時期
歯の治療を行う最適な時期は、妊娠中期(16週~27週頃)です。
妊娠初期は胎児の重要な器官が作られる時期のため、できるだけ安静に過ごすことが大切です。
また、妊娠後期になると治療時の体位が母体に負担となることがあるため、この時期の治療はできるだけ避けるのが望ましいとされています。
妊娠初期(~15週)
妊娠初期は、体調不良やつわりが強く出ることがあり、切迫流産などのリスクもある時期です。
妊娠4〜8週の治療は特に慎重に行い、12週までは主に診査や治療計画の確認、歯みがき(ブラッシング)指導などにとどめます。
歯の痛みや歯ぐきの腫れなど急な症状がある場合には応急処置を行い、本格的な治療は安定期に入ってから開始するようにしています。
妊娠中期(安定期:16~27週頃)
妊娠中期は、胎児が胎盤によって安定する時期で、歯科治療も比較的安心して行える時期です。
必要に応じてレントゲン撮影や投薬も可能となり、赤ちゃんやお母さんへの影響に配慮しながら、むし歯や歯周病などの治療に取り組むことができます。
妊娠後期(28週以降)
妊娠後期は、早産などのリスクを避けるため、歯科治療は応急的な処置にとどめることが多くなります。
お腹が大きくなることで仰向けでの治療が負担になることもあるため、この時期に本格的な治療を行うことは避け、出産後に改めて治療を再開するようにしています。
当院で行うマタニティ歯科ケア
- 妊娠週数や体調に合わせた無理のない治療計画
- 妊娠中でも安心して受けられる歯のクリーニング・予防処置
- 出産後を見据えた母子の口腔ケアアドバイス
- つわりで歯みがきがつらい方へブラッシング指導・工夫のアドバイス
産後のデンタルケア

出産後は育児に追われて自分のケアが後回しになりがちですが、産後のデンタルケアはとても大切です。
妊娠・出産によるホルモンバランスの変化で歯ぐきが炎症を起こしやすく、歯周病が進行しやすい状態になります。また、不規則な生活や睡眠不足で歯みがきが十分にできないことから、むし歯のリスクも高まります。
むし歯菌は唾液を通して赤ちゃんにうつるため、ママのお口の健康は赤ちゃんのむし歯予防にも直結します。
産後こそ意識して歯科検診や日々のケアを心がけることが大切です。
赤ちゃんと一緒にご来院ください

当院では、産後のママが安心して通えるよう、バリアフリー設計でベビーカーのまま入れる広めの診療室をご用意しています。
ぜひ赤ちゃんとご一緒にお越しください。スタッフ一同、ママのサポートはもちろん、赤ちゃんにお会いできるのを楽しみにしております。